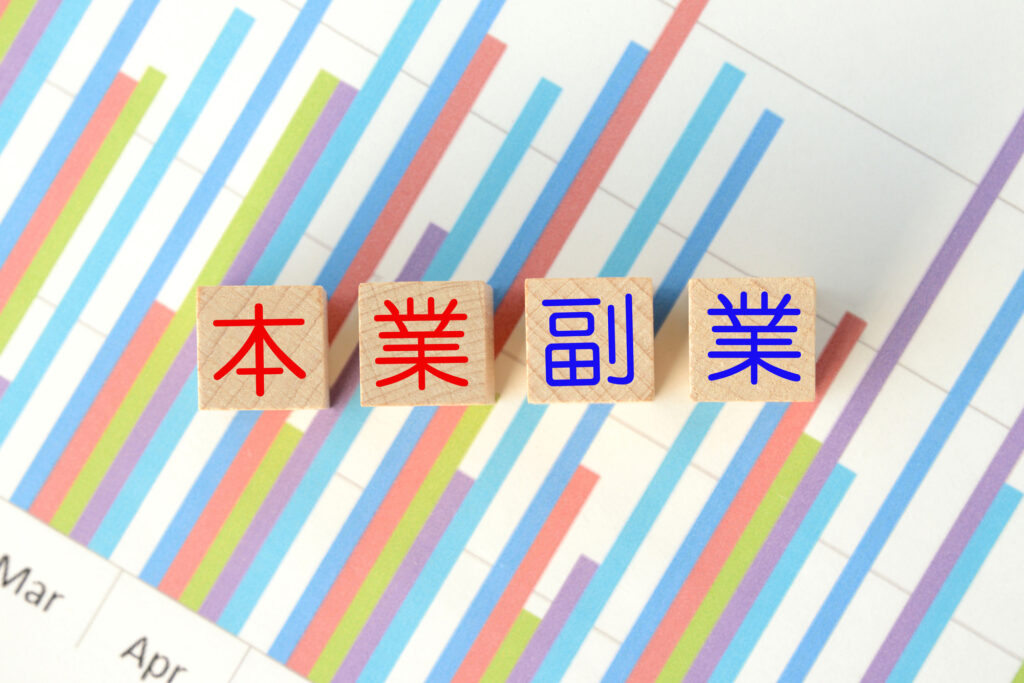二拠点生活/副業・兼業のためのポータルサイト
二拠点生活 / 副業・兼業のためのポータルサイト

デュアルライフ(二拠点生活)に役立つ・タメになる情報を発信!
副業禁止のルールは絶対? 企業に勤めながら副業を行う上での注意点を解説
副業にチャレンジしてみたいと考えていても、「本業の企業との兼ね合いはどうなるのか」「法律などで禁止されているのではないか」といった本業の勤務先に関する悩みを抱えている方は少なくないでしょう。そこで今回は、企業の副業禁止のルールについて、「法的な根拠はあるのか」「どのような背景で禁止されているのか」などについて詳しく解説します。
そもそも企業の副業禁止ルールは違法?

そもそも企業が副業を禁止することに法的な根拠はあるのでしょうか。まずは、副業と法律の関係について確認しておきましょう。
副業の定義
副業とは、本業を持つ人がそれ以外の方法で収入を得ることを指します。たとえば、会社員の方が週末にフリーランスとして仕事をしたり、本業の就業時間後にアルバイトなどをしたりするといったケースが該当します。
また必ずしも労働をともなうとは限らず、株式投資などで収入を得ることを副業と表現するケースもあります。
副業は法律上禁止されていない
そもそも副業をすること自体は法律上禁止されているわけではありません。憲法において、何人も職業選択の自由を有することが定められているため、基本的には本業の勤務時間以外であれば自由に副業を行えるはずです。
2018年1月に厚生労働省が提示している「モデル就業規則」には、多様な働き方を認める潮流から、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」という規定を新たに設けています。
ただし、副業の禁止は法律ではなく会社の就業規則で定められているため、就業規則を確認することが大切です。
公務員の副業には制限がある
基本的に法律で副業を禁止するようなルールは設けられておらず、むしろ憲法では自由な働き方が保証されています。しかし、公務員では、「国家公務員法」と「地方公務員法」によって、副業が原則禁止されているので注意が必要です。
企業が副業を禁止する理由とは?

企業が副業を禁止するという考え方は、どのような背景から生まれるのでしょうか。そこで、副業が禁止される主な理由を見ていきましょう。
長時間労働の助長につながる
副業の制限につながる背景の1つには、「長時間労働による弊害の予防」があげられます。労働契約法第5条には「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されており、企業には従業員に対する安全配慮義務があるとされています。
安全配慮義務の観点から言えば、副業を認めてしまうと結果として長時間労働を助長してしまう可能性があると考えられます。長時間労働によって、労務の提供などに支障をきたしてしまうリスクを避けるため、副業を禁止・制限するといったケースが多いのでしょう。
情報漏洩のリスク
副業が禁止されるもう1つの理由として、「情報漏洩のリスクを避ける」ことも考えられます。副業によって従業員が複数の企業で働けるようになれば、自社の業務上の秘密が漏れてしまうリスクが生まれてしまいます。
そのため、秘密保持の観点から副業を禁止・制限する規定には合理性があると考えられています。また「競業避止義務」の観点からも、副業の禁止・制限には妥当性があると考えられます。特に自社の従業員がライバル関係にある企業の業務も請け負う場合には、情報漏洩などによる損失はさらに大きくなってしまうでしょう。
副業で懲戒処分対象になるケースとは?

副業で懲戒処分の対象になってしまうかどうかは、就業規則に副業禁止規定が定めてあるかどうかが重要なポイントとなります。その上で、懲戒処分の対象となりやすい具体的なケースについて、厚生労働省が策定した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」をもとに見ていきましょう。
労務提供上の支障がある
「業務中に副業の作業をする」「副業によって本業の生産性が落ちる」など、本業の労務提供に明確な支障をきたしている場合には、懲戒処分を受けてしまう可能性があります。
ただし、企業側の判断はあくまでも慎重に行い、職場の秩序に影響が及んでいるかどうかといった点も考慮する必要があるとされています。
業務上の機密漏洩の可能性
本業で得た顧客データや技術情報などを漏洩した場合には、企業に大きな損害を与える恐れがあるため、懲戒処分の対象となる可能性があります。
自社の利益が競業他社によって害される
就業規則に規定があるにもかかわらず、競業他社を副業先とし、それによって本業の企業の利益を侵害してしまった場合には懲戒処分の対象となるケースがあります。たとえば、本業の顧客に対して、競合他社のサービス・製品を提供した場合には、本業の企業の利益を侵害したとみなされる可能性が考えられます。
自社の名誉・信用を損なう又は信頼関係の破綻
副業によって、本業の企業の信用を損なうような行動があった場合も懲戒処分を受ける可能性があります。たとえば、副業が火災保険の申請サポートなどのグレーな業務であった場合には、本業の企業にとって重大な信用失墜行為に該当する恐れがあります。
副業による懲戒処分の種類とは?

一言で懲戒処分と言っても、処分の重さには大きな違いがあります。そこで7種類の懲戒処分について、それぞれの内容をご紹介します。
戒告
「不適切な行動を戒めて反省を促す」という意味であり、懲戒処分の中ではもっとも軽い処分にあたります。厳重注意と表現されるケースもあり、口頭で済ませる場合が多いです。
ただし、対象の従業員が行った不適切な行動については、懲戒処分の事実を通して、基本的に全従業員に周知されます。そのため、単なる個人的な指導と比べれば、重い処分であるとみなされます。
けん責
戒告よりも少し重い処分にあたり、「始末書の提出によって自らの行為を反省させる」内容です。人事評価などに影響する場合がありますが、より重い処分と比べて制裁金などは課せられないケースが多いです。
減給
一定の期間にわたって賃金を減給される処分です。金額の範囲は労働基準法で定められており、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと」「総額は1賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えないこと」が上限とされています。
たとえば、平均賃金が1日あたり1万円(月給30万円)の従業員が減給処分を受ける場合、1回の限度額は5,000円までとなります。また複数回にわたって処分が行われる場合でも、限度額は月給(1賃金支払い期における賃金総額)の10分の1以内とされているので、3万円までとなります。
出勤停止
一定期間にわたって就業が禁止されるとともに、その期間の給与は無給となる処分です。具体的な期間は対象となる行為や影響度の大きさによっても異なりますが、通常は7日間から長くても1ヶ月程度とされています。 停止期間は無給となるため、減給処分よりも経済的な制裁の程度は大きくなるでしょう。
降格
企業が強制的に役職の降下・手当の減額などを行う処分です。基本給や手当が継続的に引き下げられるため、経済的な制裁の度合いは出勤停止以上に大きくなります。
懲戒処分の中では、退職を除けば「降格」がもっとも重い処分です。そのため、企業側も副業による損失の重大性などを踏まえて、慎重に検討します。
諭旨解雇
諭旨(ゆし)解雇とは、企業側から自主的な退職届の提出を勧め、それに応じない場合には解雇するという処分です。従業員としての身分を失わせる重い処分ですが、退職金を支払う企業が多い点が特徴です。
そのため、通常は解雇しなければならないほどの重大な違反をしたり大きな損害をもたらしたりした従業員に対して、情状酌量の余地などを鑑みて下される処分であるケースが多いです。
懲戒解雇
懲戒処分の中でもっとも重いのが、懲戒解雇です。通常の解雇とは異なり、「予告なしの即時解雇となる場合がある」「退職金などの支給がない」点が大きな特徴です。
対象者の人生や生活に与える影響が非常に大きいため、懲戒解雇された従業員が不当解雇として訴訟を行うケースもあります。そのため、企業も懲戒解雇に対して十分な妥当性があるかどうか慎重に検討した上で判断します。
副業を行う際の注意点

副業を行う際に注意しておきたいポイントを見ていきましょう。
就業規則で副業が禁止されていないかを確認
まずは、本業の企業の就業規則で副業が禁止されていないかどうか確認しておく必要があります。懲戒処分の対象となるかどうかは、就業規則の内容が基本的な判断基準となります。
また禁止はしていませんが、副業を始めるためには企業からの許可が必要なケースも少なくありません。予期しないトラブルを避けるためには、勤め先の就業規則にはしっかりと目を通すことが大切です。
正確な労働時間を把握しておく
労働基準法では「1日8時間以内・週40時間以内」を基本的な法定労働時間として定めており、この時間を超過すると割増賃金が発生します。また勤務先が2つある場合には両者の労働時間が合算され、後から契約をした会社には割増賃金が発生します。
そのため、フリーランスとして仕事を受けるのではなく、他の企業にも勤める形で副業を行う場合は、合計の労働時間が法定労働時間を超過しないように自分で管理することも大切です。
まとめ
副業をするかどうかは、基本的に個人の自由意志に任せられています。しかし、企業が就業規則によって禁止・制限することは可能であり、ルールを破れば規約違反として懲戒処分の対象となってしまうリスクもありますので、要注意です。
ただし、日本国内でも多様な働き方を認める動きが生まれているため、副業に関する規定に柔軟性を持たせている企業も多くあります。副業を行う際には、本業の企業が設ける就業規則にきちんと目を通して、必要があれば許可を取るなどしてトラブル予防に努めることが大切です。
※この記事は2023年12月現在の情報を基に作詞しています。今後変更されることもありますので、ご留意ください。