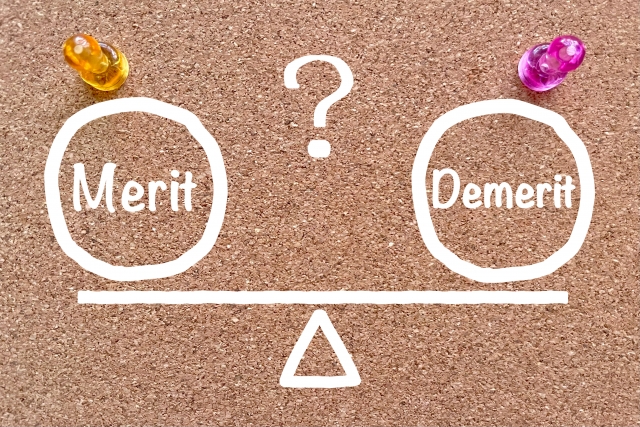二拠点生活/副業・兼業のためのポータルサイト
二拠点生活 / 副業・兼業のためのポータルサイト

デュアルライフ(二拠点生活)に役立つ・タメになる情報を発信!
多拠点生活での仕事はどうする?実践方法や具体的なステップを紹介
リモートワークが普及し、より柔軟な暮らし方・働き方を求めて多拠点生活を始める人が増えています。複数の拠点を持てば、都会と地方のメリットを同時に享受することが可能です。
一方で「今の仕事をどうするか」「安定した収入を得ながら生活を送れるのか」など、多拠点生活に不安を抱いている人もいるでしょう。
そこでこの記事では、多拠点生活で仕事を続ける・確保する方法について、メリットやデメリットも含めて詳しく解説します。
「多拠点生活」なら場所に縛られず仕事ができる

多拠点生活とは、都会や地方に複数の住処を持ち、生活スタイルに合わせて各拠点に移動しながら暮らすことです。複数拠点を使い分けて行き来することで、場所に縛られずに仕事ができます。
拠点にはシェアハウスや賃貸、空き家などさまざまな選択肢があり、近年では多拠点生活向けの「住宅サブスクサービス」も増えています。
なお、二拠点生活(デュアルライフ)が2か所での生活を想定しているのに対し、多拠点生活は複数の地域や場所に住むライフスタイルであり、より柔軟な暮らし方が実現可能です。
多拠点生活が注目される背景
多拠点生活が注目される主な理由として、以下の3つが挙げられます。
・テレワークの普及:場所に縛られない働き方により、会社の近くに住むメリットが薄れつつある
・価値観の多様化:家族の在り方や生き方にさまざまな価値観が生まれている
・地方創生や空き家活用政策:地方の過疎化が進み、国内で地方創生や空き家活用が進んでいる
特に、コロナ禍をきっかけに働き方や価値観が変化したことで、より自由で豊かな暮らしを求めて多拠点生活を始める人が増加しています。
多拠点生活を実践している人の割合
国土交通省が発表した「二地域居住等の最新動向について(令和4年度)」によると、アンケート調査を実施した全国の18歳以上の男女約12万人のうち、二地域居住等(三拠点以上の居住形態も含む)を行っている割合は約6.7%です。6.7%を18歳以上の人口(約1億495万人)に当てはめると、約701万人がニ地域居住等を実施していると推計されます。
そして、実践者の約7割が、二地域居住等に「満足・やや満足」と回答しています。二地域居住等を継続する理由としては「リフレッシュできる」「生きがいを感じる」といった前向きな意見が多く見られました。
金銭的負担の軽減や時間的な余裕の確保など課題はあるものの、多くの人が多拠点生活に魅力やメリットを感じており、今後も広まると考えられるでしょう。
多拠点生活で仕事を確保する3つの方法

多拠点生活は、仕事とプライベートのバランスをより良く保つことができる魅力的なライフスタイルです。しかし、多拠点生活で安定した収入を得る事が出来るのか、不安に感じる方は多いでしょう。ここでは、多拠点生活で仕事を確保する3つの方法をご紹介します。
会社に許可を得て仕事を続ける
今の仕事を続けながらでも、土日や連休を利用して移住すれば、多拠点生活を実現できます。平日は都会で仕事をして、休日は地方でのんびりと過ごす方法が一般的です。
転職活動をする負担がないほか、収入が減る心配もないため、気軽に多拠点生活を始められるでしょう。 ただし、拠点間を移動する時間が必要なため、連休がないと実現は難しいかもしれません。また、会社によっては多拠点生活を認めていないケースもあります。
リモートワーク可能な会社に転職する
出社する日を減らし、より自由な生活スタイルを実現したい場合は、リモートワークに対応している会社に転職することも選択肢の一つです。 リモートワークの条件は会社によって異なりますが、基本的には通勤する必要がないため、メインの生活拠点を地方にして、必要なときのみ都会で過ごすという暮らし方ができます。拠点間の頻繁な移動が不要なことから、交通費も抑えられるでしょう。
独立・起業する
フリーランスとして独立すれば、時間をもっと自由に使えるようになり、多拠点生活がしやすくなります。特に、エンジニアやWebライター、デザイナーなど、IT系やクリエイティブ系の仕事は場所に縛られずに働けるケースが多く、多拠点生活を始めるのに最適です。
また、今までのスキルを活かして仕事の幅を広げることで、収入が上がる可能性もあるでしょう。一方で、独立すると福利厚生がなくなる、収入が不安定になりやすいといったデメリットもあるため注意が必要です。
多拠点生活・二拠点生活のメリット

多拠点生活・二拠点生活の主なメリットは以下のとおりです。
・都会と田舎の両方に住処を持てる
・地域の人々との交流が深まる
・災害対策になる
最大のメリットは、都会の利便性と、自然豊かな地方の落ち着きを同時に享受できることです。仕事や生活にメリハリが生まれるため、ストレス解消につながり、より自分らしい暮らしを実現できるでしょう。また、新たな拠点でさまざまな人々と交流することで、視野を広げられる点も魅力です。
さらに、万が一災害が起こった場合、ほかの地域に住処があれば避難場所として利用できます。
※デュアルライフのメリットやデメリットについて詳しく知りたい方はこちらから。
多拠点生活・二拠点生活のデメリット

一方で、2つ以上の住処を持つことには、以下のようなデメリットや注意点もあります。
・家賃や交通費、家具費用がかかる
・住居の維持管理の手間が増える
・職業によっては負担が大きくなる
複数の拠点を構えるためには多くのコストが必要です。拠点間を移動する費用も発生するため、経済的に大きな負担となるおそれがあります。拠点が多いほど、維持管理の手間も増えるでしょう。
また、多拠点生活はセキュリティ面でも懸念があります。留守にしている住居では、空き巣などに狙われるリスクがあります。
そのほか、職業によってはリモートワークや連休を取ることが難しく、そもそも多拠点生活を始められないかもしれません。特に、出社や店舗勤務が多い仕事は多拠点生活のハードルが高いため、転職や独立なども視野に入れましょう。
多拠点生活を始めるステップ

多拠点生活を成功させるためには、事前の準備が欠かせません。生活面やコスト面において、しっかりと計画を立てておかないと、大きな負担やトラブルが発生するおそれがあります。
ここからは、多拠点生活を始める具体的な流れと注意点を解説します。
1. 目的を明確にして候補地を選ぶ
まずは、多拠点生活を始める目的や、やりたいことを明確にします。「趣味を楽しみたい」「仕事とプライベートのバランスを取りたい」など、目的がはっきりすると拠点を決めやすくなります。
目的が決まったら、拠点間を移動する頻度や移動距離などもふまえて、候補の移住先をピックアップしましょう。地域によっては、地元の祭りの手伝いや清掃活動、消防団の業務などを課されることがあるため、事前に確認しておくとトラブルを防げます。
2. 家族の理解を得る
家族がいる場合は、多拠点生活のイメージや必要なコストを共有し、一人ひとりの理解を得ることが大切です。家族の協力なしでは、多拠点生活のスムーズな実現はできません。
夫婦間だけではなく、子どもともよく話し合い、問題点や不安なことを洗い出しておきましょう。滞在期間によっては、子どもの学校に関する話し合いも必要です。
3. 資金計画を立てる
多拠点生活にかかる費用を把握し、無理のない資金計画を立てましょう。新たな拠点を構えるには、初期費用として敷金や礼金、家財道具の購入費がかかります。
以下は、多拠点生活でかかる費用の内訳の一例です。
【初期費用(賃貸の場合)】
- 敷金:家賃1〜2か月分
- 礼金:家賃0〜2か月分
- 日割り家賃:入居日に応じて計算
- 仲介手数料:家賃0〜2か月分
- 火災保険料
- 家具・家電の購入費用
- 鍵の交換費用
- 引っ越し費用
【ランニングコスト】
- 家賃
- 水道光熱費
- 通信費
- 日用品費
- 交通費
- 車の維持費(ガソリン代、駐車場代、車検代など)
4. 物件を確保して仕事環境を整える
自分たちのライフスタイルや多拠点生活の目的に合った物件を選び、契約します。自治体の担当者や地元の不動産業者などに相談して情報を集めると、スムーズに進められるでしょう。
多拠点生活をする物件には、さまざまな選択肢があります。家族と一緒であれば一戸建て、単身であればシェアハウスやサブスクサービスなどを活用した暮らし方も検討してみてください。物件を確保したら、ネット環境の整備や家具の購入など、仕事や生活をするうえで必要な準備を進めていきます。
なお、多拠点生活を始める際に住民票を移す場合は、市役所での転居手続きが必要です。引っ越し前に転出届、引っ越したあとに転入届を出します。滞在時間が長いほうの拠点に住民票を置くケースが一般的ですが、家族と相談し、どの地域の公的サービスを受けたいのかを考えて選びましょう。
多拠点生活にはサブスクサービスが便利

多拠点生活が注目を集めるなか、徐々に広まっているのが「住まいのサブスク」サービスです。月々定額を払えば、日本全国の空き家や宿泊施設が住み放題になるサービスで、気軽に二拠点生活や多拠点生活を始められるメリットがあります。
住まいのサブスクは、基本的には1ヵ月単位の契約のサービスもあり、利用期間を自由に選ぶことが可能です。生活に必要な家具家電付きで、敷金礼金も必要ありません。水道光熱費も月々の利用料金に含まれているサービスも多いです。
滞在先を気軽に変更でき、自分に合った地域を見つけられるサブスクサービスの利用を、ぜひ検討してみてください。
※「住まいのサブスクリプション」について詳しく知りたい方はこちら。
まとめ

多拠点生活で仕事を確保するには「会社に許可を得て仕事を続ける」「リモートワーク可能な会社に転職する」「独立・開業する」といった方法があります。特に、リモートワークなどで場所にとらわれない働き方ができれば、多拠点生活がますます身近なものになるでしょう。
近年では、住まいのサブスクサービスを活用し、気軽に多拠点生活を実践する人も増えています。自分に合ったライフスタイルや働き方で、多拠点生活を始めてみてはいかがでしょうか。
※この記事は2025年2月現在の情報を基に作成しています。今後変更されることもありますので、ご留意ください。