二拠点生活/副業・兼業のためのポータルサイト
二拠点生活 / 副業・兼業のためのポータルサイト

秋田内陸縦貫鉄道株式会社 秋田県北秋田市
“空から鉄道へ”。CAを副業人材として受け入れ、豊富な知見や客観的な視点を業務に活用。
秋田県北秋田市の鷹巣駅から仙北市の角館駅までの総延長約95kmを結ぶ、秋田内陸線。沿線に四季折々の美しい景色が広がり、多くの観光客が乗車するこの鉄道を運営するのは、北秋田市に本社を構える秋田内陸縦貫鉄道株式会社です。同社では2024年5月から2025年4月まで、業務提携先である全日本空輸株式会社(以下、ANA)グループから3名のキャビンアテンダント(以下、CA)を副業人材として受け入れました。今回はCAの知見や視点を鉄道業務に活用した事例についてご紹介します。
ANAグループの現役CA3名を受け入れ。
ユニークなデュアルライフや働き方として、新聞やテレビなどでも取り上げられた今回の事例について、受け入れの相談から3名の人選、マネジメント調整などを行った秋田内陸縦貫鉄道の総務企画部長・長澤学さんにお話を伺いました。

元々、大館能代空港が沿線に近いこともあり、ANAグループとはさまざまなコラボレーション企画を実施していたという同社。ANAグループの社員が多様な働き方を実践するための方法を模索する中、長澤さんはCAの副業先として相談を受けました。
「おそらく先方としては、取引先として信頼できる会社であること、相乗効果がある会社ということで、弊社にお声掛けいただいたのではないでしょうか」と長澤さんは、人材不足の解消や従業員の成長に期待して、受け入れを決めたと言います。「弊社としては求人で苦労している中、ダブルワークでも構わないので人の流れを生み出したいと思っていました。また、CAとしての知識や知恵、安全に対する姿勢などを共有してもらうことで、社員にとって良い影響が与えられるのではないかと考えました」。
受け入れにあたって、秋田内陸縦貫鉄道ではオンラインで会社の説明会を実施。「約20名の方にご参加いただき、新しい働き方への関心の高さが伺えました」と長澤さん。その後、副業として秋田県庁に勤務し、秋田内陸線を題材にしたフォトエッセイを作成した経験があるという原さん、秋田県出身の児玉さん、祖父母が秋田県出身ということから秋田で働いてみたかったという廣田さんの3名の受け入れを決定。月8日を上限に同社で勤務してもらうことになりました。
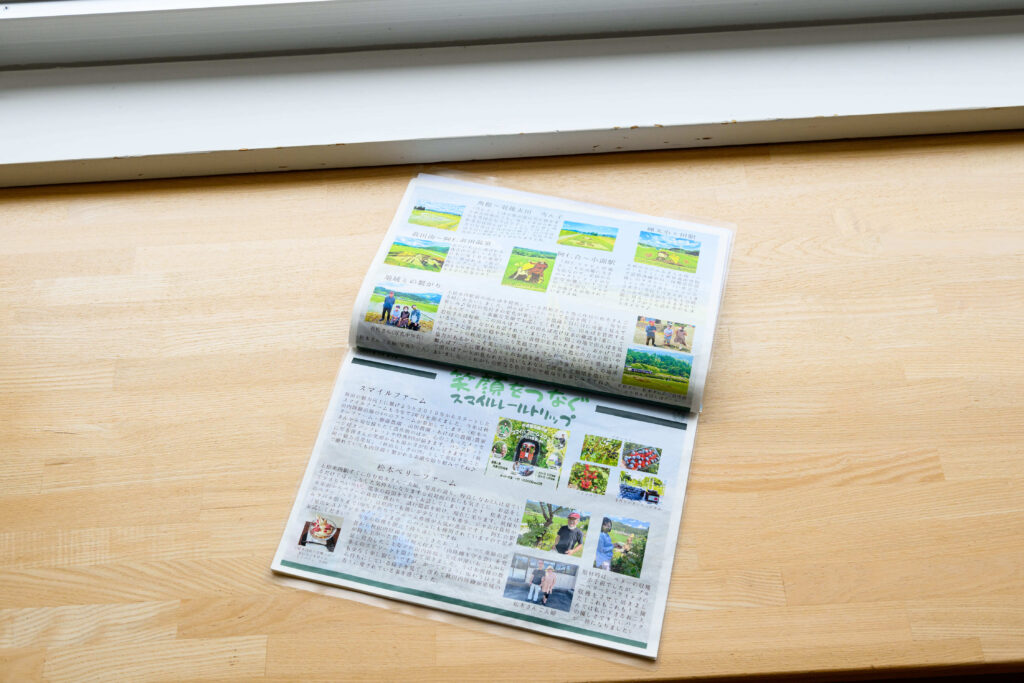
客観的な視点や接客スキルに期待。
3名のうち、原さんと児玉さんは企画職に配属され、イベントや商品の企画立案といったデスクワークを中心に、イベント会場での作業や取引先との調整などにも当たりました。「地元出身者が多い社内の人間では、地域外の人にとっては魅力的なものでも見落としてしまうことがあります。2人の新鮮な視点に期待しました」と長澤さんは説明します。実際に2人はこれまで同社が行ってきた、沿線物の農産物や伝統工芸品をパッケージにして販売する「スマイルファーム」という企画を担当。沿線の農家や生産物の管理者のもとに出向き、交渉して商品化を実現したそうです。「2人ともフットワークが軽いので、トライ&エラーを繰り返して商品づくりに励んでくれました。以前は扱いのなかった商品をパッケージに入れ込んだり、我々にも新たな発見がありました」。
一方、廣田さんは秋田内陸縦貫線で乗務員として接客などを行う観光アテンド職に就きました。「ANAさんで鍛えられたアナウンス力だったり、お客様に寄り添い、伝える力はとても高く、弊社の観光アテンダントにも共有してもらい、全体としてレベルアップできたと思います。また、朗らかな人柄もあって、お客様に積極的に話しかけられている場面もよく見られました。お客様の楽しい旅の思い出として刻まれていたら、ありがたいですね」。

また、副業をした3名にとっても秋田内陸縦貫鉄道での業務は、大きな経験となったようです。「3人は充実感を感じながら、仕事をしてもらっていたようです」と長澤さんは、人事評価の面談などを通じた反応について教えてくれました。「企画職の2人はCAと全く違う職種だったので、実務的に苦労している面もあったようです。しかし、今回の副職の目的の一つが“自分の幅を広げる”ということでもあったので、仕事を楽しんでいました。また、廣田さんは同じアテンド職ということもあり、違和感なく仕事をされていましたね。鉄道と飛行機で客層が違うことを面白がっていて、普段とは異なる客層のお客様との触れ合いから刺激を受けていると聞きました」。
多様な働き方を成功に導くために大切なこと。
今回の受け入れについて長澤さんは「3人の壁を作らない人柄や積極性もあり、会社に活気が生まれましたし、重要な戦力となりました。本人たちも『自分でこうしてみたい』という意欲も高く、新しい企画やサービス、接客の仕方につなげられたと思っています」と話してくれました。秋田内陸縦貫鉄道が3名を受け入れ、社内外に好影響を与えることができた要因について伺うと、以下の3点を挙げてくれました。
1つ目は、会社の方針をしっかりと伝えたこと。第3セクター鉄道※としての地域での在り方について、オリエンテーションなどで丁寧に説明したそうです。「私たちは民間企業ではなく、第3セクター鉄道なので地域の公共インフラであり、地域の皆さんのためにある会社です。利益だけを追求するのではなく、いかに地域の役に立てるのか考えてほしいと伝えました。そういった意味も込めて、受け入れ後すぐ地域の皆様の元へ挨拶回りを行い、いろいろな言葉を聞いてもらいました。そうすることで内陸線がどう思われているのか、立ち位置を理解していただきました」。
※国や地方公共団体(第1セクター)と民間企業(第2セクター)が共同で資金を提供し、運営を行う鉄道のこと。
2つ目は、受け入れ前に希望者とのコミュニケーションを綿密に行ったこと。「会社が求めるものと応募者の求めるものをすりあわせて、しっかりマッチングしていれば、その後も問題なく進めていけるはずです」。
そして3つ目が、社内で受け入れ体制を築いておくことです。「受け入れる人たちの思いを社内の皆で共有することが大事ではないでしょうか。受け入れてから『あの人、少ししか来ないじゃない!」というようになってはいけませんよね。弊社では3人の人柄もありましたし、事前に受け入れ部署などを共有していたことで、皆が柔軟に受け入れてくれました。新しい働き方や多様性を受け入れられる社内体制が必要だと思います」。

一方で大変だった点について伺うと、「主業のシフトを考慮しながら仕事のマネジメントを行った点ですね。ただ、長期スパンで臨めるようなものや他の人がサポートしやすい業務などをお願いすることで、しっかりと成果を出すことができました」と長澤さん。また、「3人には他の業務にも従事してもらいたかったのですが、限られた勤務時間の中では難しい面がありました」と答えてくれました。
最後にデュアルライフや副業の展望について、長澤さんご自身の考えを伺いました。「これからどんどん人口が減っていく中、企業でも人材の奪い合いが進みます。また、AIが人の代わりに行う仕事も増えるでしょうし、多様な働き方を受け入れなければいけなくなるはずです。そうなるのであれば、今から徐々に新しい働き方を受け入れ、業務に活用する姿勢でいた方が将来のさまざまな可能性に繋げられると思います」。
今後、副業やデュアルライフ希望者の受け入れを検討している企業の方は、ぜひ今回の事例を参考にしてみてはいかがでしょうか。




